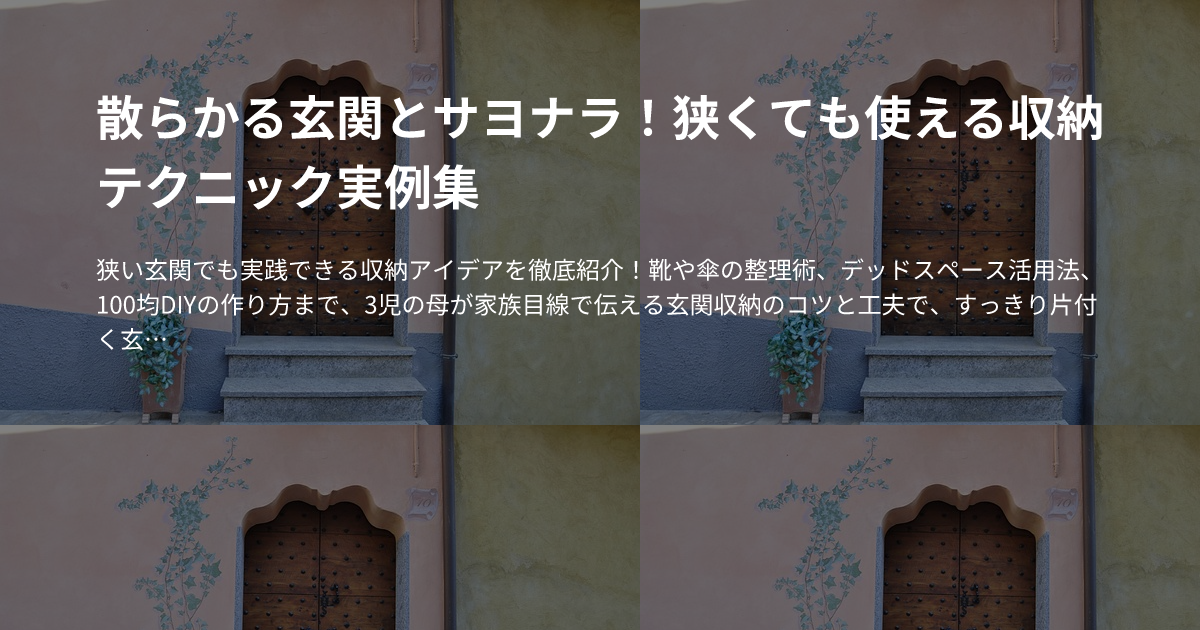玄関先収納の重要性と基本的な考え方
玄関は家の顔であり、一日の始まりと終わりに必ず通る場所です。家族全員が使う玄関がごちゃごちゃしていると、朝の忙しい時間に必要なものが見つからずイライラしたり、帰宅時に疲れた心がさらに疲れてしまいます。まずは玄関収納の基本的な考え方から見ていきましょう。
玄関先収納の3つの基本原則

玄関先の収納を考える上で、まず押さえておきたいのが3つの基本原則です。
1つ目は「出し入れのしやすさ」です。 毎日使うものほど取り出しやすい場所に配置することが重要です。 特に朝の忙しい時間帯は、靴や鞄、家の鍵などをサッと取り出せるようにしておくと、家族の出発がスムーズになります。 私の家では、子どもたちが自分で靴を取り出せるよう、一番下の棚に子ども用の靴を並べています。
2つ目は「見える収納と見えない収納の使い分け」です。 頻繁に使うものは見える位置に、たまにしか使わないものは見えない場所に収納するとメリハリがつきます。 特に来客の多いご家庭では、見せたくないものは扉付きの収納に隠し、見せても良いものだけを開放棚に置くと印象がぐっと良くなりますよ。
3つ目は「定位置を決める」ことです。 家族全員が「ここに置く」というルールを共有することで、探し物が減り、片付けもスムーズになります。 我が家では玄関に家族一人ひとりの名前付きフックを設置しているので、鍵や通学カバンの定位置が一目でわかるようになっています。
家族構成別・必要な収納量の目安

玄関収納を考える際に意外と見落としがちなのが、家族構成に合わせた収納量の確保です。
一般的に大人一人あたり5〜10足、子ども一人あたり3〜8足の靴のスペースが必要になります。 さらに季節の変わり目には、次のシーズンの靴も出してくるため、一時的に収納量が増えることも想定しておきましょう。 我が家は5人家族なので、常時40足ほどの靴が玄関に並ぶ計算になります。 これを見越して、玄関だけでなく、廊下の一角にもオフシーズンの靴を収納できるスペースを確保しています。
また、家族の趣味や仕事にも注目です。 スポーツをする子どもがいれば専用シューズが必要になりますし、仕事で靴を使い分ける方がいれば、それだけ収納スペースも必要になります。 私の夫は営業職なので、複数の革靴を使い分けています。 そのため、夫用の靴収納は特に余裕を持たせて確保しています。
さらに、傘や帽子、手袋など季節の小物の収納も忘れずに。 特に梅雨時は家族全員分の傘の置き場所に困ることが多いので、コンパクトな傘立てや壁掛けフックなどを活用するといいでしょう。
狭い玄関先でも実践できるスペース活用術
「うちの玄関は狭いから…」とあきらめていませんか?実は、限られたスペースだからこそ効果的な収納方法があります。私も6畳一間から始まった新婚生活時代から、様々な住居で工夫してきました。壁や床、ドアの裏側など、見落としがちなスペースを有効活用するテクニックをご紹介します。
縦の空間を活かす収納術

狭い玄関でまず注目したいのが「縦の空間」です。 床から天井までの高さを最大限に活用することで、限られた面積でも収納力をアップできます。
最も手軽なのは突っ張り棒タイプのシューズラックです。 床から天井まで伸びるポールに棚を何段も取り付けられるタイプは、工具不要で設置できて便利です。 我が家でも廊下の一角に設置して、子どもたちのスニーカーを収納しています。 上部の棚には使用頻度の低い靴を置き、手の届きやすい中段・下段には日常的に使う靴を配置すると使いやすくなりますよ。
壁面を活用する方法もおすすめです。 ウォールシェルフやウォールポケットを取り付けると、靴以外の小物も美しく収納できます。 私は玄関の壁に小さなウォールポケットを付けて、子どもたちの通学定期や防犯ブザーなど、小さくてもすぐに必要なものを入れています。 朝の「あれどこ?」が激減して、時間のロスがなくなりました。
天井近くのデッドスペースも見逃せません。 高い位置に棚を設置すれば、季節外れの靴やメンテナンス用品など、頻繁には使わないものの収納場所として活用できます。 ただし、高い位置の収納は取り出しにくいので、年に数回使う程度のものに限定すると良いでしょう。 我が家では、スキー靴やスノーブーツなど冬季限定の大型靴を、夏場はこの高い位置に収納しています。
デッドスペースを有効活用する方法

玄関には意外と多くのデッドスペースが存在します。 これらを見つけて活用することで、収納力が格段にアップします。
まず注目したいのが、玄関ドアの裏側です。 ドアフックを利用すれば、傘やコート、エコバッグなどをコンパクトに収納できます。 扉を開けている時しか見えない場所なので、見た目も気になりません。 我が家では子どもたちのレインコートをここに掛けていますが、いざという時にサッと取れるので便利です。
シューズボックスと壁の間の隙間も貴重なスペース。 わずか10〜15cmの隙間でも、専用のすき間収納を置けば傘立てやブーツ収納として活用できます。 私はこの隙間に細長いラックを置いて、長靴や折りたたみ傘を収納しています。 見た目もすっきりして、出し入れもしやすいのでお気に入りの場所です。
玄関の上がり框(かまち)の下も見逃せません。 靴を脱ぐスペースと室内の間の段差部分ですが、この下に空間がある場合は、引き出し式の収納ボックスを設置できることも。 我が家ではここに防災用の簡易スリッパを収納していますが、普段は全く目につかないので玄関の見た目を損ねることがありません。
シーズンオフアイテムの保管方法

限られた玄関スペースを効率よく使うには、シーズンオフのアイテムをどう管理するかが鍵となります。 適切な保管方法で次のシーズンも気持ちよく使えるようにしましょう。
基本的な考え方は「今使わないものは玄関の一等地に置かない」ということ。 サンダルやブーツなど、明らかに季節限定の靴は、使わない時期は玄関から撤去するのが原則です。 我が家では季節の変わり目に家族総出で「靴の衣替え」をします。 今シーズン使う靴を玄関に出し、使わない靴は廊下の収納や押入れに移動させています。
保管する際のポイントは「清潔にしてから収納する」こと。 特に冬用のブーツは塩分や汚れがついたまま保管すると、革が傷んだり、カビが生えたりします。 我が家では収納前に必ず中性洗剤で軽く洗い、陰干しで十分に乾かしてから専用の袋に入れています。 少し手間ですが、次のシーズンに気持ちよく履けるので大切にしています。
また、型崩れ防止も重要です。 ロングブーツには専用のブーツキーパーや丸めた新聞紙を入れておくと、次のシーズンも美しいフォルムを保てます。 子どもの靴は成長で履けなくなることも多いので、シーズン終わりには必ずサイズチェックして、小さくなっていれば思い切って手放すことも大切です。
効果的な収納アイテムの選び方と活用法
玄関収納アイテムは種類が豊富で選ぶのに迷ってしまいますよね。ホームセンターやインテリアショップに行くと、色々な商品が並んでいて「どれが我が家に合うのかな?」と考え込んでしまうことも。今回は、私が実際に使って便利だった収納アイテムと、その選び方のポイントをご紹介します。
シューズラックの選び方と活用術
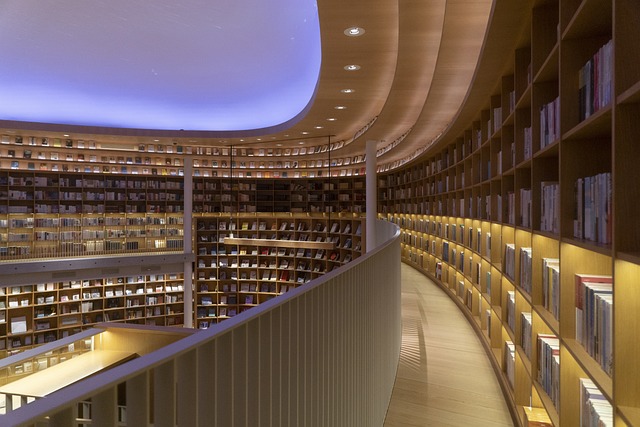
シューズラックは玄関収納の主役ともいえるアイテム。 選ぶ際のポイントと、上手な活用方法をご紹介します。
まず重要なのが「棚板の間隔」です。 一般的な靴の高さは7〜10cm程度ですが、ブーツや子どものスニーカーなど高さのあるものもあるため、高さ調節できるタイプが便利です。 我が家では高さ調節ができるメッシュタイプのシューズラックを使っていますが、季節や靴の種類に合わせて棚板の位置を変えられるので重宝しています。
次に「通気性」も大切な要素。 靴は湿気を含みやすいので、風通しの良いメッシュタイプや隙間のあるスチール製のものがおすすめです。 私が以前使っていた木製のシューズボックスは見た目が良かったのですが、湿気がこもりやすく、梅雨時期にカビが生えてしまったことがありました。 今はオープンタイプのラックに変えて、通気性を重視しています。
また「設置場所に合わせた形」も考慮しましょう。 狭い玄関なら薄型タイプ、横幅に余裕があれば横長タイプなど、空間に合わせて選ぶことが大切です。 我が家は廊下からつながる玄関で横幅が限られていたため、縦長のタワー型シューズラックを採用しました。 奥行きが20cmほどと薄いので、通路をふさがず使いやすいです。
シューズラックは靴以外の収納にも活用できます。 最上段に小物入れを置いたり、側面にフックを取り付けたりすることで、多機能な収納スペースになります。 我が家のシューズラックの上には、仕切り付きのボックスを置いて、家族それぞれの鍵や定期券を整理しています。
玄関で活躍する便利な小物収納グッズ

靴以外にも、玄関には様々な小物が集まります。 それらをすっきり収納する便利グッズをご紹介します。
まず重宝するのが「マグネットフック」です。 玄関ドアの内側や、スチール製の靴箱の側面に取り付けられ、鍵やエコバッグなどの定位置に最適です。 工具不要で付け外しができるので、賃貸住宅でも安心して使えます。 我が家では子どもたちの学校の鍵をマグネットフックに掛けていますが、目線の高さに付けることで、子どもたち自身が管理できるようになりました。
「ウォールポケット」も便利なアイテムです。 壁に取り付けるタイプの布製ポケットで、手紙や郵便物、子どものお道具袋など、平たいものの一時置き場として活用できます。 我が家では玄関の壁に8ポケットタイプのものを取り付け、家族それぞれの小物管理に役立てています。 「明日持っていくもの」を前日に入れておくことで、朝の忘れ物防止にも一役買っています。
「傘立て」も工夫次第で使いやすくなります。 最近は折りたたみ傘と長傘を一緒に収納できるタイプや、傘の水滴を受け止める水受け付きのものもあります。 狭い玄関なら、ドア裏につけるフックタイプの傘掛けもスペースを取らず便利です。 我が家は玄関の隅にスリムな傘立てを置き、折りたたみ傘は別にウォールフックを設置して掛けるようにしています。
「靴べら」や「消臭剤」など、玄関小物の定位置も確保しておきましょう。 特に靴べらは長さのあるものが使いやすいですが、置き場所に困ることも。 壁掛けタイプの靴べらホルダーを活用すれば、すっきりと収まり、必要な時にサッと取り出せます。 我が家では玄関ドアの横に長い靴べらを掛ける専用フックを付けています。
下駄箱の中を整理する方法

玄関に備え付けの下駄箱がある家庭も多いでしょう。 効率よく使うためのコツをお伝えします。
まず基本は「靴を揃えて入れる」こと。 当たり前のようですが、これだけで収納効率と見た目が格段に良くなります。 特に子どもがいるご家庭では、かかとを手前に揃えるよう習慣づけると、取り出しやすく、片付けも簡単になります。 我が家では「かかとピタッ」というフレーズを合言葉に、子どもたちにも靴を揃える習慣をつけました。
「シューズボックス内の仕切り」も活用すると便利です。 プラスチック製の仕切りや100均の小物入れを使えば、靴の種類ごとに区分けでき、取り出しやすくなります。 私は下駄箱の中に簡易なラックを追加して、2段収納にしています。 パンプスやペタンコ靴など高さのないものは2段に並べることで、限られたスペースを最大限に活用できています。
「下駄箱の扉裏」も見逃せない収納スペース。 100均などで売っている粘着フックを付ければ、靴べらや防臭剤、靴ブラシなどの小物を掛けられます。 我が家の下駄箱の扉裏には小さなメッシュポケットを取り付け、靴ひもの予備や靴の消臭スプレーなどを収納しています。 目に見えない場所なので生活感も隠せて一石二鳥です。
また、「シーズン別に分ける」工夫も有効です。 下駄箱の上段には現在のシーズンの靴、下段にはオフシーズンや使用頻度の低い靴を入れるなど、使いやすさを考慮した配置を心がけましょう。 特に小さなお子さんがいる家庭では、子どもが自分で取り出せる高さに子どもの靴を配置すると、自立心を育むのにも役立ちます。
DIYで作る玄関先収納アイデア
市販の収納グッズを買うのも良いですが、予算や理想のサイズが見つからない場合は、DIYで作ってみるのも一つの選択肢です。私自身、子どもが小さい頃は予算も限られていたので、手作りアイテムで玄関収納を工夫してきました。今回は初心者でも挑戦できる、シンプルなDIY収納アイデアをご紹介します。
100均素材で作る靴収納ラック

100均の素材を組み合わせるだけで、使い勝手の良い靴収納ラックが作れます。 初心者でも簡単にトライできるDIYをご紹介します。
最も簡単なのは「ワイヤーネットを使った靴ラック」です。 100均で売っているワイヤーネット数枚と、連結用のパーツを使って組み立てるだけ。 必要な幅や高さに合わせて自由に設計できるのが魅力です。 私も子どもたちの靴用に作りましたが、成長に合わせて高さを変えられるので長く使えています。 ワイヤーの隙間から空気が通るので、湿気対策にもなっているのがうれしいポイントです。
「すのこを活用した靴ラック」も人気のDIYです。 100均やホームセンターで手に入るすのこを2〜3枚重ねて、釘やビスで固定するだけ。 側面に脚を付ければ、通気性抜群の靴ラックの完成です。 我が家ではすのこラックをペイントして、玄関のアクセントカラーと合わせました。 見た目も可愛く、家族からも好評です。
「牛乳パックで作るブーツキーパー」も簡単な上に、コストゼロで作れるのでおすすめ。 牛乳パックを洗って乾かし、高さを調節してカットします。 表面を好みの包装紙や布で覆えば見た目も良くなります。 私も長靴やブーツの中に入れて型崩れ防止に活用していますが、ちょうどいい硬さで効果抜群です。
どのDIYも工具はハサミやカッター、場合によってはドライバーがあれば十分。 休日の午後に子どもと一緒に取り組めば、楽しい家族の時間にもなりますよ。 我が家の子どもたちも「自分で作ったから大切にする」と言って、靴の片付けを進んでするようになりました。
壁掛け小物収納の作り方

壁を活用した小物収納も、簡単なDIYで作ることができます。 傘や鍵、手紙などをすっきり収納する方法をご紹介します。
「古いフレームを活用したキーフック」は見た目も可愛く実用的です。 不要になった写真立てや額縁の裏側に小さなフックを取り付けるだけ。 フレームの見える面はお気に入りの布や壁紙を貼ると、インテリア性もアップします。 我が家では古い木製フレームをサンドペーパーで磨いて白くペイントし、鍵掛けに活用しています。 家族ごとに色分けしたフックを付けることで、誰の鍵かすぐに分かるようにしました。
「木の板を使ったマルチラック」も便利です。 30cm×40cmほどの板を壁に取り付け、下部にフックを付けるだけで、傘や帽子などが掛けられるスペースの完成です。 上段の平らな部分には小物を置けるので、手紙や小銭入れなどの一時置き場としても活用できます。 我が家では玄関の壁に取り付け、季節のインテリア小物と一緒に飾っています。 見た目も良く、来客時に「どこで買ったの?」と聞かれることも多いDIYです。
「ペットボトルを再利用した壁掛けポケット」も環境にやさしいDIYです。 2Lのペットボトルを横半分にカットし、カラフルな布やリメイクシートで覆います。 壁に固定すれば、手紙や小物が入れられるウォールポケットの完成です。 子どもの下校後のお手紙入れとして活用すれば、重要な連絡事項も見落とさずに済みます。
いずれのDIYも必要な材料費は1,000円以下で作れるものばかり。 「センスがない」と思う方でも、ネットや雑誌などを参考にすれば、素敵なアイテムが作れますよ。 世界に一つだけのオリジナル収納で、毎日の玄関の出入りが楽しくなります。
簡単シューズトレーのDIY

雨の日や雪の日に大活躍する「シューズトレー(靴置き)」も、DIYで簡単に作れます。 濡れた靴を直接床に置かず、水受けとして活用できる便利アイテムです。
最も簡単なのは「プラスチックケースの活用」です。 100均などで売っている浅いプラスチックケースに、キッチンマットやバスマットの切れ端を敷くだけ。 靴についた水分を吸収してくれるので、床が濡れる心配がありません。 我が家では子ども一人につき一つのケースを用意して、名前を書いています。 「自分の靴は自分のトレーに」というルールで、玄関の水濡れも防げて片付けもスムーズです。
「すのこを使ったシューズトレー」もおすすめです。 小さなすのこの下に防水シートや浅いトレーを敷けば、雨や雪で濡れた靴の水切りになります。 すのこ部分が靴底に触れるため、床が濡れず、靴も乾きやすいというメリットがあります。 我が家では玄関の隅にL字型に設置して、家族全員分の濡れた靴の置き場を確保しています。
「タイルで作るおしゃれなシューズトレー」も見た目が良いDIYです。 ホームセンターで売っている安価なタイルを組み合わせ、防水加工を施せば、玄関をセンスアップさせる靴置きになります。 私の友人宅では、モザイクタイルでデザインした靴トレーが素敵なアクセントになっていて、とても参考になりました。
DIYシューズトレーのポイントは「お手入れしやすさ」です。 定期的に水洗いできる素材を選んだり、取り外して干せる構造にしたりすると、清潔を保ちやすくなります。 特に梅雨時期や冬は頻繁に使うアイテムなので、メンテナンスのしやすさも考慮して作りましょう。
家族全員が使いやすくなる工夫
どんなに素敵な収納システムを作っても、家族が使いこなせなければ意味がありません。特に小さな子どもや高齢の方と一緒に暮らしている場合は、全員が使いやすい工夫が必要です。3人の子どもを育てながら試行錯誤してきた経験から、続けられる収納の仕組み作りのコツをお伝えします。
子どもでも使える収納の工夫

子どもが自分で靴の出し入れができるようになると、朝の準備がグッとスムーズになります。 子どもの自立心を育てる玄関収納のコツをご紹介します。
まず大切なのは「子どもの目線の高さに収納を配置する」こと。 大人にとっては少し低い位置でも、子どもにとっては使いやすい高さになります。 我が家では下駄箱の一番下の段を子ども専用にし、自分で靴を取り出し、片付けられるようにしています。 自分でできる喜びを感じられるため、靴の片付けも進んでするようになりました。
「目印をつける」工夫も効果的です。 子どもの靴収納場所に名前シールを貼ったり、カラーボックスを使う場合は色分けしたりすると、「どこに片付けるか」が一目でわかります。 我が家では子どもの顔写真と名前を収納ボックスに貼っていますが、まだ字が読めない小さな子どもでも自分の場所がわかるようになっています。
「履きやすい向きで収納する」ことも重要です。 特に小さな子どもは、靴の向きを考えるのが難しいもの。 常に履く向き(つま先が外側、かかとが内側)で収納しておくと、自分で履く時にスムーズです。 我が家では「かかとをこっちに」と声掛けして習慣づけしていますが、履き間違いが大幅に減りました。
また「靴の数を制限する」のも実は大切なポイント。 子どもに必要な靴は意外と少なく、普段履き、運動靴、長靴、サンダルなど数足あれば十分です。 あまり多くの靴を用意すると収納も難しくなるので、本当に必要な数に絞るのがおすすめです。 我が家では子ども一人につき5足までと決めて、古くなったら新しいものに買い替える方式にしています。
シニアにも使いやすい収納の工夫

年配の方と同居されているご家庭では、安全性と使いやすさを考慮した収納がポイントです。 体の負担を減らす工夫をご紹介します。
一番のポイントは「中腰姿勢を減らす」ことです。 高齢になると靴の脱ぎ履きで腰を曲げる動作が負担になります。 玄関に安定した椅子やベンチを置くことで、座りながら靴の脱ぎ履きができ、転倒防止にもなります。 私の両親宅では玄関に折り畳み式のコンパクトなスツールを置いていますが、靴の脱ぎ履き時の安全確保に役立っています。
「頻繁に使う靴は手の届きやすい位置に」というのも基本中の基本。 毎日履く靴は棚の奥や高い場所ではなく、取り出しやすい位置に配置しましょう。 理想的には腰から胸の高さで、深く屈まなくても手が届く場所がベストです。 我が家の義父は腰痛持ちなので、専用の靴ラックを玄関横に設置し、屈まずに靴の出し入れができるようにしています。
「長い靴べらの活用」も忘れてはいけません。 立ったままでも靴が履きやすい長めの靴べらを、取りやすい位置に設置しておきましょう。 壁掛けタイプなら場所も取らず、必要な時にすぐ手に取れます。 我が家では70cmほどの長い靴べらをドア横に掛けていますが、子どもから高齢の家族まで重宝しています。
また「滑り止め対策」も重要です。 玄関マットには滑りにくいタイプを選び、特に雨の日の転倒防止に配慮しましょう。 吸水性に優れたマットを室内外両方に敷くことで、床が濡れて滑りやすくなるのを防ぎます。 私の両親宅では玄関の内外に大きめのマットを敷き、靴底の水分をしっかり拭き取れるようにしています。
みんなで続けられる収納ルール作り

どんなに良い収納システムを作っても、家族全員が協力しなければすぐに元の散らかった状態に戻ってしまいます。 長続きする収納ルール作りのコツをお伝えします。
まず大切なのは「シンプルなルール設定」です。 複雑すぎるルールは守られません。 「靴は必ず棚に入れる」「傘は水を切ってから立てる」など、基本的なルールを2〜3個に絞りましょう。 我が家では「かかとをそろえて入れる」「使った靴べらは元の場所に戻す」「外出用の鞄は自分のフックに掛ける」の3つを基本ルールとしています。
「見える化」も効果的です。 特に小さな子どもには、イラスト付きのルール表を作ると理解しやすくなります。 玄関に小さなボードを設置して、靴の収納方法を絵で示すと、視覚的に理解しやすいでしょう。 我が家では「靴の収納場所マップ」を作り、家族全員の靴の定位置を明確にしています。 新しい靴を買った時も、このマップに追加するので混乱がありません。
「定期的な見直し」も継続の秘訣です。 季節の変わり目や長期休みに、家族で一緒に玄関収納を見直す時間を作りましょう。 使わなくなった靴や不要になったアイテムを整理し、収納スペースを再確認します。 我が家では年に4回、季節の変わり目に「玄関整理デー」を設けていますが、この習慣のおかげで玄関が常にすっきりしています。
何よりも大切なのは「褒める文化」を作ること。 特に子どもは褒められることで行動が定着します。 「靴をきれいに並べてくれてありがとう」「自分で片付けられるようになったね」など、小さな成長も見逃さず褒めましょう。 我が家では「玄関美化大賞」といって、一週間で一番きれいに靴を片付けられた人を表彰する遊びを取り入れています。 子どもたちはこれを楽しみにしながら、進んで片付けるようになりました。
まとめ:快適な玄関生活のために
今回ご紹介したように、玄関先の収納は工夫次第で大きく改善できます。 狭いスペースでも縦の空間を活用したり、デッドスペースを見つけたりすることで、驚くほど収納力がアップするのです。
特に重要なのは、家族全員が使いやすいシステムを作ること。 子どもからお年寄りまで、それぞれの特性に合わせた高さや取り出しやすさを考慮することで、自然と片付く玄関が実現します。
DIYでオリジナルの収納を作れば、予算を抑えながらも理想の収納が手に入ります。 100均アイテムや家にあるものを活用すれば、コストをかけずに素敵な収納が作れることもお分かりいただけたと思います。
最後に、継続できるルール作りを忘れずに。 どんなに素晴らしい収納システムも、家族が協力して維持しなければ意味がありません。 シンプルなルールと定期的な見直しで、いつもすっきりとした玄関を保ちましょう。
玄関は一日の始まりと終わりに必ず通る場所。 ここがきれいに整っていると、気持ちよく出発でき、ホッとして帰宅できます。 ぜひ今日からできることから少しずつ始めて、家族みんなが使いやすい玄関収納を作ってくださいね。