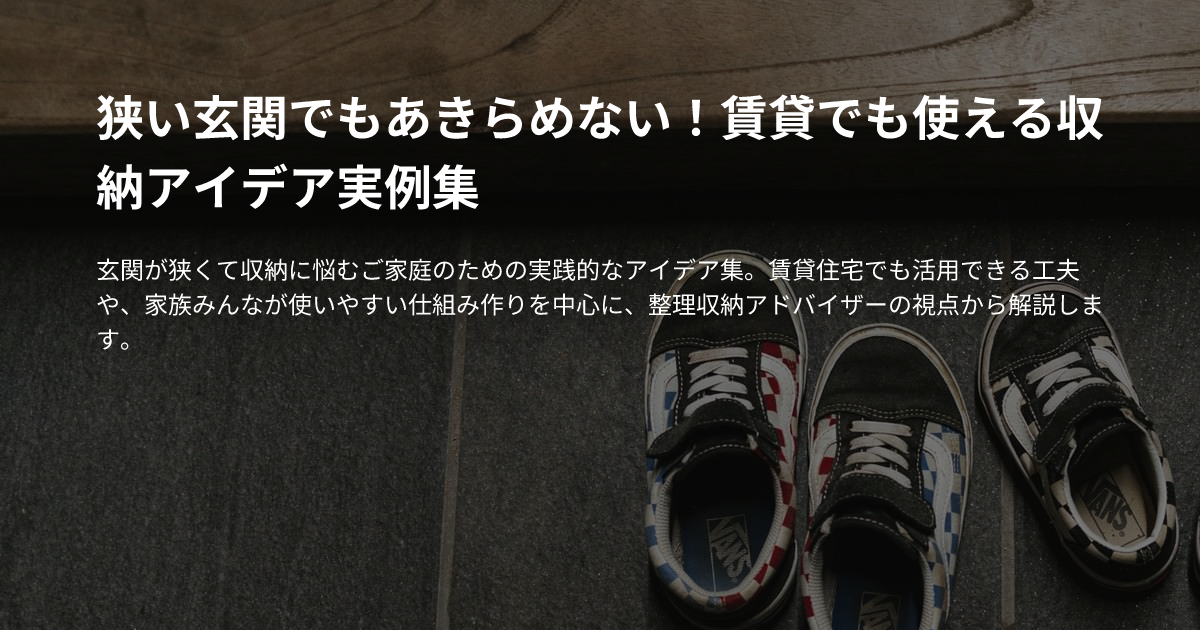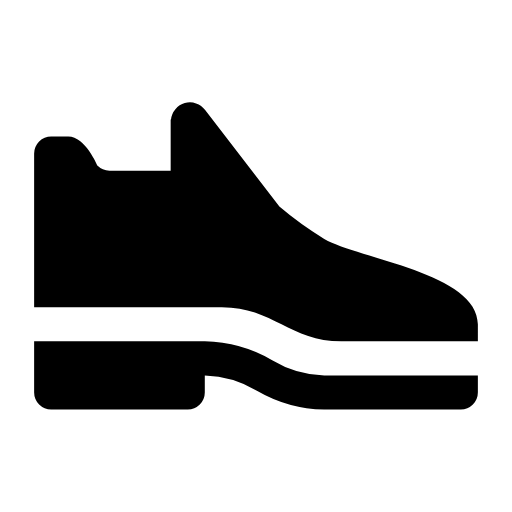玄関の可能性を広げる3つの視点
「うちの玄関は狭すぎて…」そんな悩みをよく耳にします。確かに日本の住宅、特に賃貸の玄関は驚くほど狭いもの。でも視点を変えれば、そこには無限の可能性が広がっています。3人の子どもと靴好きの夫を持つ私が試行錯誤の末に見つけた、狭い玄関を劇的に使いやすくする3つの視点をご紹介します。
狭い玄関の3つの課題
狭い玄関で多くの方が直面する課題は、主に3つあります。
1つ目は「絶対的なスペース不足」です。4人家族なら単純計算で20足以上の靴が必要になりますよね。わが家も長男のサッカーシューズ、次男の長靴、末っ子のお気に入りサンダルと、靴だけで溢れかえっていました。これに季節品や来客用を加えると…考えただけでため息が出ます。
2つ目は「動線の悪さ」です。物が多いと靴を取り出すのも一苦労。「ママ、靴が見つからない!」と子どもが叫ぶ朝は、本当に焦りますよね。私も以前は長男の靴を探して遅刻しそうになったことが何度もありました。限られたスペースでの動線確保は、特に忙しい朝には重要なんです。
3つ目は「湿気と臭いの問題」です。靴は外から汚れや湿気を持ち込むもの。狭いスペースに密集していると、どうしても湿気や臭いがこもりやすくなります。特に梅雨時は気になりますよね。実は玄関収納を考える際、この「目に見えない問題」への配慮も必要なんです。
可能性を最大化する考え方
でも大丈夫!狭い玄関にも無限の可能性があります。大切なのは視点を変えること。
まず重要なのは「立体的に考える」こと。床面積が限られているなら、壁や天井までの空間を活用しましょう。わが家でも壁面収納を取り入れたら、収納量が2倍以上になって驚きました。お子さんの幼稚園バッグや帽子も壁のフックに掛けるだけで、床はすっきり片付きますよ。
次に大切なのは「適材適所」の発想です。毎日使う靴と特別な時だけの靴、お子さんの靴と大人の靴など、使用頻度や用途で分けましょう。わが家では子どもたちの靴は手の届く低い位置に、パパの仕事用革靴は上の段に、と分けています。こうすれば朝の支度もスムーズになりますよ。
そして何より「続けられる仕組み」が重要です。どんな素敵な収納方法も続かなければ意味がありません。特にお子さんがいるご家庭では、子どもが自分で片付けられる工夫が必須です。わが家では子どもの目線の高さに名前入りのボックスを置いたところ、3歳の末っ子でも「ここに入れるんだね」と喜んで片付けるようになりました。
まずは仕分けから始めよう!玄関すっきり3ステップ
どんな収納を考える前にも、まずは「仕分け」が大切です。物が多すぎる玄関をすっきりさせるには、何を残して何を別の場所に移すか、しっかり見極める必要があります。3人の子ども服や靴で溢れかえっていた我が家の玄関も、この「仕分け」のおかげで生まれ変わりました。今日からできる簡単3ステップをご紹介します。
全て出して「見える化」する
収納改善の第一歩は、玄関のものを全て出して「見える化」することです。
休日のまとまった時間(2時間程度)を確保して、思い切って全部出してみましょう。靴はもちろん、傘、コート、バッグなど、一時も欠かさず全部です。わが家でこれをやったとき、「こんなに物があったの!?」と家族全員で驚きました。特に子どもの成長に合わなくなった靴や、いつの間にか増えた傘の多さには本当にびっくり。
この「見える化」は、玄関という空間を新鮮な目で見直す良い機会になります。床や壁のスペース、コンセントの位置なども確認してみてくださいね。「あ、この隙間にスリムな棚が入りそう」「ここにフックを付けられそう」など、新たな発見があるはずです。わが家でも壁の出っ張りに目をつけて、そこにコート掛けを設置したら大正解でした!
ついでに普段手が届かない場所の掃除もしてしまいましょう。子どもたちにも手伝ってもらうと、「玄関をみんなで気持ちよく使おう」という意識が自然と生まれますよ。わが家では「ピカピカ作戦」と名付けて、子どもたちも楽しみながら参加してくれています。
3つのボックスで仕分ける
出したものは3つのカテゴリーに分けていきましょう。これが整理の鉄則です。
私がいつも使っているのは「残す」「手放す」「別の場所へ」という3つの分類です。「残す」は玄関に置いておくもの、「手放す」は処分や譲渡するもの、「別の場所へ」は玄関以外に移動させるものです。迷ったら「本当にここに必要?」と自問自答してみてください。わたしも最初は「いつか使うかも」と思って残していた靴がたくさんありましたが、思い切って見直してみると、半分以上は別の場所に移しても困らないものでした。
「残す」ものを選ぶ際のポイントは「使用頻度」と「緊急性」です。毎日使うものや急な外出時に必要なものは玄関に、それ以外は思い切って別の場所へ移しましょう。フォーマルな靴やシーズンオフのブーツなどは、クローゼットなど別の収納スペースがベストです。わが家ではシーズンオフの靴は全てベッド下収納ボックスにしまい、玄関をすっきりさせています。
特にお子さんのアイテムは成長に合わせて定期的な見直しが必要です。うちの場合、子どもの靴は3ヶ月に一度チェックする習慣にしています。小さくなった靴は思い出の1足以外は思い切って手放すか、下の子に譲るようにしています。子どものものって本当にすぐにサイズアウトしちゃいますよね。
シーズンで分ける発想
玄関収納スペースを倍増させる秘訣は「シーズン分け」です。これは本当におすすめ!
一年中すべての靴やアウターを玄関に置いておく必要はないんです。現在の季節に必要なものだけを玄関に、オフシーズンのものは別の場所に保管する習慣をつけましょう。例えば夏場はサンダルやスニーカーを玄関に、ブーツや厚手のコートはクローゼットや押入れに。この単純な工夫だけで玄関スペースが約2倍になるんですよ。わが家では季節の変わり目に家族の「衣替え」と一緒に「靴替え」も行っています。
シーズン切り替えのタイミングは、春と秋の衣替えと一緒だと忘れにくくて便利です。わが家では5月と10月の最終週末にシーズン切り替えをする習慣にしています。子どもたちにとっても「サンダルの季節が来た!」と季節の変化を感じる良い機会になっているんですよ。家族イベントとして取り組むと、子どもたちも進んで協力してくれます。
オフシーズンの靴の保管方法として私がおすすめするのは、クリアボックスの活用です。100均やホームセンターで手に入る透明なプラスチックボックスに、きれいに手入れした靴を入れて押入れやクローゼットの上段に保管します。透明なボックスなら中身がすぐわかるので、「あれ、どこにしまったっけ?」という心配もありません。靴の中には乾燥剤を入れておくと、カビ予防にもなりますよ。
垂直方向の空間を賢く使う工夫
狭い玄関の収納力を劇的に高めるには、床だけでなく「上への視点」が欠かせません。壁・ドア・天井に向かって伸びる空間には、まだまだ活用できる可能性がいっぱい!賃貸でも壁を傷つけずにできる垂直収納の工夫を、家族5人でも窮屈さを感じない工夫を重ねてきた私の経験からご紹介します。
賃貸でもできる壁面収納
賃貸住宅では壁に穴を開けられないことが多いですが、それでも壁面を活用する方法はたくさんあります。
まず活用したいのが「突っ張り棒」です。玄関の壁と壁の間に突っ張り棒を設置し、S字フックを使って帽子やバッグ、傘などをかけられます。高さを変えて複数設置すれば、家族それぞれの身長に合わせた収納が可能になりますよ。わが家では子どもの背の高さに合わせた低い位置の突っ張り棒と、大人用の高い位置の突っ張り棒を設置しています。小さな子でも「自分で取れる・しまえる」というのが大切なんです。
次に便利なのが「コマンドフック」などの粘着タイプのフックです。跡が残らず取り外せるので賃貸でも安心して使えます。鍵やマスク、子どものお出かけ帽子などの小物類をかけるのに最適ですよ。ドアの内側や下駄箱の側面など、これまで見落としていたスペースも活用できるんです。わが家では子どもごとに違う色のフックを用意して、「青はお兄ちゃん、赤は次男」というように分けています。子どもも自分の色を覚えて、ちゃんと自分の場所に掛けてくれるようになりましたよ。
また「つっぱり式シューズラック」も賃貸住宅での強い味方です。床置きではなく天井と床の間に突っ張るタイプのシューズラックは、穴を開けずに設置できて倒れる心配もありません。最近のものは薄型で玄関ドアの動線を邪魔しないデザインも多いので、狭い玄関でも活用できます。わが家も以前の賃貸マンション時代は、このタイプのラックで15足以上の靴をすっきり収納していました。
ドア裏の隠れスペースを活用
意外と見落としがちなのが「ドアの裏側」という貴重なスペースです。これは本当におすすめですよ!
玄関のドア裏は、実は収納の宝庫なんです。ドアフックを使えば、コートやバッグ、傘など、かさばるアイテムを効率よく収納できます。特に来客時にはドアを開けておくことが多いので、一時的に見えなくなり、急な来客でも慌てずに済みますよ。わが家ではドア裏に子どもたちのレインコートや学校の体操服袋をかけています。急な雨の日も「あれどこ?」と探さなくて済むので便利なんです。
ドア裏用のポケット収納も便利です。100均やニトリなどで手に入るドア用ポケットオーガナイザーを活用すれば、手袋や折りたたみ傘、マスクなどの小物類をすっきり収納できます。透明ポケットタイプなら中身が一目でわかるので、忙しい朝でもサッと必要なものを取り出せますよ。特に子どもの手袋やマフラーなど、なくしやすい小物の収納に最適です。
ドア裏収納のポイントは「薄さ」です。あまり厚みのあるものを設置すると、ドアの開閉に支障が出る可能性があります。設置前にドアの開閉をシミュレーションして、問題ないか確認しておきましょう。わが家では実際に設置する前に、段ボールで厚みを確認するという方法で失敗を防いでいます。ちょっとした工夫で後悔しない選択ができますよ。
浮かせる収納で床を広く見せる
狭い玄関を広く見せるコツは「床を見せること」です。これは見た目も実用性も両立する素敵な方法です。
床に直接物を置くと、それだけで狭く感じてしまいます。反対に、収納を床から浮かせると、床面積が見える分だけ広さを感じられるんです。賃貸で壁に棚を付けられない場合でも、脚の細いシューズラックや、床置きでも高さのあるタイプを選ぶと床が見え、空間に余裕が生まれます。わが家も昨年下駄箱を床置きタイプから脚付きタイプに変えただけで、玄関が格段に広く感じるようになりました。見た目の印象って大事ですよね。
床を見せるメリットは見た目だけではありません。「床の掃除がしやすい」という実用面でも優れています。玄関は外からの砂やホコリが入りやすい場所。床との間に隙間があると掃除機やフロアワイパーが入りやすく、日々のお手入れが格段に楽になります。3人の子育てをしながら家事もこなす私にとって、掃除の手間が減るというのは本当に大きなポイントなんです。時短につながる工夫は、ぜひ取り入れたいですよね。
さらに、床から浮かせる収納は湿気対策にもなります。特に日本の高湿度な気候では、床に直接靴を置いておくと湿気がこもりやすく、カビの原因になることも。風通しの良い浮かせる収納なら、靴の乾燥も早く、清潔に保ちやすいという利点もあります。私も以前は靴の臭いや湿気に悩んでいましたが、収納方法を変えてからはその問題もかなり解消されましたよ。
100均&ニトリで作る!続けられる収納の秘訣
お金をかけなくても、工夫次第で素敵な玄関収納は実現できます。大切なのは「続けられること」。高価な収納家具よりも、家族のライフスタイルに合った使いやすい仕組みの方が長続きするんです。3人の子育てに奮闘しながら、試行錯誤で見つけた100均やニトリのアイテムを活用した、家族みんなが無理なく続けられる収納アイデアをご紹介します。
靴収納のアイデア
靴は玄関収納の中でも最も場所を取るアイテム。効率的な収納方法を工夫しましょう。
100均のファイルボックスは、実はブーツやスニーカーの収納に最適なアイテムなんです。スリッパやサンダルなど小さな靴なら1つのボックスに2〜3足も収納できます。縦に置くと靴が見やすく取り出しやすいので、特に子どもの靴収納に便利ですよ。わが家では子どもごとに色分けしたファイルボックスを用意して、「赤いボックスは長男の靴」というように分けています。子どもたちも自分の色を覚えて、ちゃんと片付けてくれるようになりました。
靴の収納で意外と見落としがちなのが「上下の空間活用」です。靴は床に平置きするより、靴用ラックで立てて収納したり、靴箱内に100均の靴収納スタンドを使ったりすることで、同じスペースに2倍近く収納できるようになります。ニトリの「立てる靴収納」は特に使いやすく、見た目もすっきりするのでおすすめです。わが家では靴箱の中にこのスタンドを入れたことで、以前より5足も多く収納できるようになりました。
ブーツなど丈の長い靴は型崩れが気になりますよね。100均のポリ袋に新聞紙を詰めたものをブーツの中に入れておくという簡単な方法で型崩れを防げます。使わない時期はクローゼットにしまっておき、玄関にはシーズンの靴だけを出しておくようにすれば、限られたスペースでも靴をキレイに保管できますよ。わが家では特に子どものレインブーツは次のシーズンまで取っておくことが多いので、この方法で型崩れを防いでいます。
傘・鍵・小物の収納テクニック
傘や鍵など、なくしやすい小物類の収納こそが玄関の使いやすさを左右します。
傘の収納には、意外にも100均の「ペットボトルホルダー」が便利なんです。壁に貼り付けるタイプのものを使えば、傘をコンパクトに立てかけられます。また、ニトリの「マグネット傘立て」は玄関ドアの金属部分にくっつけられるので、床スペースを全く使わずに傘を収納できる優れものです。わが家では子ども用の小さな傘とおとな用の傘を分けて収納し、出かける時に「自分の傘は自分で持つ」習慣をつけています。子どもも小さなことから自立の第一歩ですね。
鍵やマスクなど小さくてもすぐに必要なものは、出入り口近くの「取りやすい・見える位置」に収納するのがポイントです。100均のマグネットフックを玄関ドアに取り付けたり、小さなかごを玄関の目立つ場所に置いたりすることで、出かける直前に「あれ、鍵どこだっけ?」となることを防げます。特に朝の忙しい時間には、この小さな工夫が大きな時間節約になりますよ。わが家ではドア横に「おでかけボックス」を設置して、鍵・マスク・ハンカチなど外出時に必ず必要なものをまとめています。
季節によって必要な小物も変わりますよね。夏は虫除けスプレーや日焼け止め、冬は手袋やマフラーなど。これらは100均の小さなかごに季節ごとにまとめ、玄関の棚やシューズボックスの上に置いておくと便利です。わが家では季節の変わり目に「季節ボックス」の中身を入れ替える作業を家族で行い、季節の変化を感じる機会にもしています。子どもたちも「今日から夏の季節ボックスだね!」と喜んで手伝ってくれるんですよ。
コートとバッグの収納術
かさばるコートやバッグの収納こそ、玄関の印象を大きく左右します。
コート収納で最も簡単なのは「つっぱり式ポールハンガー」の活用です。壁を傷つけずに設置できて、意外な収納力があります。最近のものは上部に小物置きがついているタイプもあり、便利ですよ。また、100均の「S字フック」を使えば、ひとつのフックに複数のアイテムをかけられるので収納力がアップします。わが家ではS字フックを使って「コート→バッグ→傘」という順で縦にかけ、セットで持ち出せるようにしています。忙しい朝の準備が格段にラクになりましたよ。
バッグの収納で困るのは、形が不安定で重なると崩れてしまうこと。そこで便利なのが100均の「仕切り板」や「ファイルスタンド」です。これらを使ってバッグを立てて収納すれば、型崩れせずにコンパクトに収納できます。ニトリの「かばん収納ラック」も、複数のバッグを効率よく収納できるのでおすすめですよ。わが家では子どものランドセルもこの方法で収納していて、朝の支度がスムーズになりました。
使用頻度の高いコートやバッグは手の届く場所に、シーズンオフや特別な場合にのみ使うものはクローゼットなど別の場所に保管するという「使用頻度による振り分け」も重要です。玄関はあくまで「日常的に使うもの」だけを置くスペースと割り切ることで、すっきりとした空間を保てます。わが家では2週間使わなかったものは「卒業」として別の場所に移動させるルールにしています。
家族みんなが使いやすい収納の工夫
家族構成によって玄関収納の悩みは変わってきます。単身者と子育て世帯では必要なものも量も全く違いますよね。わが家も子どもの成長とともに収納の仕方を何度も見直してきました。家族それぞれのライフスタイルに合った、みんなが使いやすい収納の工夫をご紹介します。一人ひとりが心地よく使える玄関は、毎日の出発と帰宅を笑顔にしてくれますよ。
単身・夫婦のコンパクト収納
単身者や夫婦のみの世帯では、シンプルでスタイリッシュな収納が可能です。
単身・夫婦世帯では、一人当たりの持ち物は多くても、全体の量はそれほど多くないのが特徴です。そのため「見せる収納」を取り入れやすく、インテリア性を重視した玄関づくりができます。例えば、壁面に設置したディスプレイシェルフに厳選した靴やバッグを飾るように置いたり、オープンラックに小物を美しく配置したりすることで、機能的でありながらおしゃれな空間に仕上がります。友人宅の単身世帯では、お気に入りの靴をあえて見せる収納にしていて、とてもスタイリッシュでした。
また、単身・夫婦世帯では「趣味のアイテム」が多い傾向があります。スポーツ用品やアウトドアグッズなど、趣味に関連する特殊な靴やバッグを収納する必要がある場合は、使用頻度によって「玄関に置くもの」と「クローゼットにしまうもの」を明確に分けましょう。週末だけ使うゴルフシューズなどは、専用のバッグに入れて別の場所に保管するといった工夫が効果的です。夫婦二人暮らしだった頃の我が家も、趣味の登山靴やテニスシューズは専用のバッグに入れてクローゼットに保管していました。
都市部のコンパクトな住まいでは「一人分のスペース」を明確にすることも大切です。夫婦それぞれの靴の場所を決めておけば、「どっちがどの靴を履いたか」で朝から探し物になることを防げます。ニトリの「仕切り板」を使って靴箱の中を区分けするだけでも、使いやすさが格段に向上しますよ。わが家も夫婦二人の頃は、靴箱の左側が夫、右側が私、という単純な仕切りで随分と使いやすくなりました。
子育て世帯の収納工夫
子育て世帯の玄関収納で大切なのは「子どもが自分で片付けられる仕組み」です。
子どもの成長に合わせた高さの収納を用意することは、自立心を育む上でも重要です。低い位置にフックを設置したり、子ども専用の靴箱を床に近い位置に置いたりすることで、小さな子どもでも自分で片付けられるようになります。わが家では「顔」のイラストをつけた子ども専用のボックスを用意したところ、2歳の末っ子でも「お顔の中に入れる」と喜んで靴を片付けるようになりました。子どもって自分でできることが増えると本当に嬉しそうですよね。
また子育て世帯では「物の量の変化」に対応できる柔軟性も必要です。子どもの靴のサイズは半年で変わることもありますし、季節や習い事によって必要なアイテムも変化します。そこで「固定の収納」ではなく「動かせる収納」を採用するのがおすすめです。100均のカゴやボックスを活用すれば、内容を入れ替えたり、配置を変えたりすることが容易になります。わが家では子どもの成長に合わせて「サッカーボックス」「スイミングボックス」など用途別の収納ボックスを増やしたり減らしたりしています。
さらに、子育て世帯では「探しやすさ」も重要なポイントです。「どこに何があるか」が一目でわかるよう、カゴにラベルを付けたり、中身が見える透明ケースを使ったりする工夫をするといいですよ。うちの長男は朝弱いタイプなので、前日に「明日の靴」を決めて、特別な場所に出しておくという習慣を作り、朝のバタバタを減らしています。こうした小さな工夫が、家族の毎日をスムーズにしてくれるんです。
共働き家庭の時短収納術
共働き家庭では「時間の節約」につながる収納が重要です。
朝の忙しい時間に探し物をしないためには「定位置管理」がカギとなります。鍵やICカード、通勤・通学に必要なアイテムは必ず決まった場所に戻す習慣をつけましょう。玄関ドア近くに家族全員分の「ポケット収納」を設置し、それぞれの必需品を入れておくと便利です。わが家では壁に100均のポケット収納を貼り、家族それぞれの名前と顔写真をつけて「自分の持ち物は自分で管理」というルールにしています。これだけで朝の探し物時間が激減しましたよ。
また、帰宅時の「置き場所」も重要です。仕事や学校から帰ってきた時に、バッグや上着をどこに置くかをあらかじめ決めておくことで、翌朝の準備がスムーズになります。ニトリの「立てかけ収納ラック」を玄関に設置すれば、カバンやリュックを立てかけられるので、床に置く必要がなくなり、見た目もすっきりします。わが家でも玄関の壁際にこのラックを置いて、ランドセルや仕事バッグの定位置にしています。
さらに、共働き家庭では週末にまとめて収納の見直しをする時間を設けるといいですよ。週に一度、家族で15分程度の「玄関整理タイム」を設け、靴を元の位置に戻したり、不要になったものを片付けたりします。この短時間の習慣が、平日の忙しい朝の混乱を防いでくれるんです。わが家では日曜の夕方に「明日から気持ちよく過ごすための玄関チェック」として実施しています。子どもたちも「月曜日を気持ちよく迎える準備」と理解して、進んで協力してくれていますよ。
賃貸でもあきらめない!工夫次第のスッキリ玄関
「賃貸だから壁に穴を開けられない」「大型の収納家具を置けない」そんな制限がある中でも、工夫次第でスッキリとした玄関は実現できます。私自身、3回の引っ越しを経験し、どの賃貸住宅でも試行錯誤しながら使いやすい玄関づくりに挑戦してきました。壁を傷つけず、退去時にも原状回復可能な、賃貸住宅向けの収納アイデアをご紹介します。
壁に穴を開けない収納術
賃貸住宅では壁に穴を開けられないことが多いですが、代替策はたくさんあります。
まず活用したいのが「突っ張り式のラック」です。床と天井の間に圧力で固定するタイプの収納家具は、壁に穴を開けずに設置できる上、安定性も抜群です。最近のものはデザイン性も高く、インテリアとしても素敵なものが多いですよ。わが家でも以前の賃貸マンションでは、突っ張り式のコートハンガーとシューズラックを組み合わせて使っていました。見た目もスッキリして、来客からも「おしゃれだね」と褒められたんですよ。
次におすすめなのが「吸着タイプのフック」です。3Mのコマンドフックに代表される粘着テープ式のフックは、跡を残さずに取り外せるので賃貸住宅にぴったり。ドアの内側や下駄箱の側面など、これまで使えなかったスペースを有効活用できます。特に子どもの目線の高さに設置すれば、小さなお子さんでも自分でコートやバッグをかけられるようになります。うちの子どもたちも、自分専用のフックがあることで、「ここに掛けるんだ!」と理解して、自分で片付けるようになりました。
また「マグネット式の収納グッズ」も賃貸住宅での強い味方です。玄関ドアが鉄製の場合は、マグネットフックや小物入れを直接ドアに取り付けられます。傘立てやキーフックなど、様々なマグネット式アイテムが販売されているので、ドアのスペースを最大限に活用しましょう。わが家では引っ越しの度に「このドアはマグネットが付くかどうか」をまず確認する習慣がついています。マグネットが使える玄関だと、収納の可能性が広がって本当に助かりますよ。
可動式収納で柔軟に対応
賃貸住宅で重宝するのが、自由に動かせる「可動式収納」です。
キャスター付きのシューズラックやワゴンは、掃除の時や来客時にサッと移動できるので便利です。特に玄関が狭い賃貸住宅では、臨機応変に配置を変えられる可動式の収納が重宝します。ニトリやIKEAには、デザイン性の高いキャスター付き収納家具が多数あり、見た目もおしゃれに仕上がりますよ。わが家でも玄関とリビングの間にキャスター付きのワゴンを置き、靴以外の小物類を収納しています。来客時にはさっと移動できるので便利なんです。
また、スタッキングできるボックスも賃貸住宅に適しています。積み重ねれば収納力アップ、分散させれば小さなスペースにも対応できるという柔軟性が魅力です。100均の同じサイズのボックスをいくつか揃えておけば、引っ越しの際にも対応しやすく、新居のレイアウトに合わせて自由に配置を変えられます。わが家でも子どもたちの小物入れとして、スタッキングボックスを愛用しています。子どもが増えたときも、ボックスを増やすだけで対応できて本当に便利でした。
さらに「持ち運べる収納」という発想も大切です。例えば布製の靴入れやハンギングオーガナイザーは、使わない時はコンパクトに畳んでしまえますし、引っ越しの際にも荷物になりません。季節に応じて出し入れする収納としても便利で、わが家では冬の間だけ玄関に設置する「手袋・マフラー用のハンギング収納」を活用しています。必要な時だけ出して使えるので、シーズンオフはクローゼットにしまっておけますよ。
原状回復を考えた工夫
賃貸住宅では「退去時の原状回復」を念頭に置いた収納選びが重要です。
まず意識したいのが「床や壁を傷つけない工夫」です。収納家具の脚部分にフェルトを貼ったり、壁に接する部分にクッション材を挟んだりするだけでも、傷や汚れを軽減できます。特に湿気の多い日本の住宅では、家具と壁の間に隙間を作ることで、カビの発生も防げるというメリットもあります。わが家では家具の下に100均の「すべり止めマット」を敷いて、床の傷防止と同時に地震対策もしています。小さな工夫ですが、退去時の修繕費を抑えることにもつながりますよ。
壁紙を傷めない工夫も必要です。粘着テープで壁紙が剥がれることを防ぐため、最近では「壁紙用フック」という専用商品も登場しています。また、壁紙の種類によって適した粘着剤が異なるので、自宅の壁紙タイプを確認してから適切な製品を選びましょう。私は以前、壁紙を確認せずにフックを貼ってしまい、退去時に修繕費を請求された苦い経験があります。皆さんはぜひその失敗から学んでくださいね。
また「一時的な改造」という発想も役立ちます。例えば、突っ張り棒を利用した棚やカーテンレール、マグネットシートを活用した小物収納など、原状回復が容易な方法を選びましょう。これらは取り外した際に跡が残りにくく、賃貸住宅でも安心して使えます。賃貸でも快適に過ごすコツは「賢く使って、きれいに戻す」という意識を持つことなんですよ。わが家では引っ越し前に「元に戻せるかな?」と一度シミュレーションしてから設置するようにしています。
玄関美人になるための習慣づくり
どんなに素敵な収納システムを作っても、日々の習慣がなければすぐに元の散らかった状態に戻ってしまいます。私も3人の子どもがいるので、「きれいにしても数時間で靴だらけ…」という経験は数え切れないほど。でも大丈夫。家族みんなで無理なく続けられる小さな習慣が、いつもスッキリした玄関を維持する秘訣なんです。今日から始められるお手軽習慣をご紹介します。
家族で取り組む15秒ルール
「15秒ルール」は我が家の玄関を救った魔法の習慣です。
このルールは単純明快。「玄関を出入りする時に、15秒だけ片付けや整理をする」というものです。たった15秒でも、家族全員が毎日実践すれば、驚くほど玄関がきれいに保てます。例えば、靴を脱いだらすぐに靴箱に入れる、散らかった靴を1足だけ整える、落ちているチラシを拾うなど、ほんの小さな行動でOKです。この習慣を家族全員が身につけると、玄関が散らかる前に常に整理された状態が維持できます。わが家では「ちょっとだけお掃除マン」と呼んで、子どもたちも楽しんで参加してくれていますよ。
我が家では「靴は履いたら履いたで、脱いだら脱いだで」という合言葉を作り、靴を履くときも脱ぐときも、その都度正しい場所に置くことを徹底しています。最初は子どもたちに定着するか心配でしたが、親が一貫して実践し続けることで、自然と子どもたちの習慣にもなりました。今では3歳の末っ子も「靴はここだよね」と言いながら片付けてくれます。親が率先して続けることが、子どもに習慣を身につけさせるコツですね。
また、習慣化のコツは「難しくしすぎないこと」です。複雑なルールや厳しい基準を設けると長続きしません。「大体この辺に置く」くらいの緩やかなルールでも、みんなが守れば十分に整理された状態を保てます。玄関収納の成功は「完璧さ」ではなく「継続のしやすさ」にあるんです。わが家でも最初は「ここにピッタリ並べる」と厳しくしていましたが、続かなかった反省から、今はもっと緩やかなルールにしています。その方が不思議と続くんですよ。
季節の切り替えと定期メンテナンス
日々の小さな習慣に加えて、定期的な「大掃除」と「季節の切り替え」も重要です。
年に2回(春と秋)を目安に、玄関の大掃除と収納の見直しをしましょう。衣替えのタイミングと合わせると忘れにくいですね。この時に、シーズンオフの靴やコート、傘などを別の収納スペースに移動させます。例えば春には冬物のブーツやコートをクローゼットにしまい、サンダルや薄手のジャケットを玄関に出すといった具合です。わが家では季節の切り替え時に「玄関衣替え祭り」と銘打って、家族全員で取り組む恒例行事にしています。子どもたちも「お祭り」と言うと喜んで参加してくれるんですよ。
また、この機会に子どものサイズアウトした靴のチェックも忘れずに。子どもの足は半年で1cm以上成長することもあるので、定期的な見直しが必要です。サイズアウトした靴は思い出の1足以外は思い切って手放すか、下の子に引き継ぐかを決めましょう。わが家では「お下がり箱」を用意して、上の子のサイズアウト品を整理しています。でも時々「これは記念に取っておこう」という特別な靴も出てきますね。そんな時は押入れの一番上の「思い出ボックス」に入れています。
定期メンテナンスでもう一つ大切なのが「収納システムの見直し」です。家族のライフスタイルや必要なものは、時間と共に変化していきます。子どもの成長、家族の趣味の変化、仕事環境の変化などに合わせて、収納方法も柔軟に見直していきましょう。「これはここに置いてあるのが当たり前」という固定観念にとらわれず、より便利な方法を常に模索する姿勢が大切です。わが家でも長男が小学生になり自転車通学が始まったときに、玄関の収納を見直して自転車の鍵や反射板の置き場所を新設しました。
子どもも参加できる仕組み作り
子どもが自ら進んで片付けたくなる「仕組み」を作ることが、長続きの秘訣です。
子どもが自分で片付けられるようにするためには、「わかりやすさ」が重要です。名前ラベルや色分け、イラストなどを活用して、「どこに何をしまうか」を視覚的に理解できるようにしましょう。わが家では各自の靴箱に顔写真と名前を貼り、「ここは○○くんの特等席だよ」と呼んでいます。子どもたちは自分の「特等席」に靴を入れることを誇りに思い、進んで片付けるようになりました。小さな子は特に「自分の場所」という意識が大事なんですよ。
また、子どもの背の高さに合わせた収納を用意することも大切です。大人目線の高さに収納を設置してしまうと、子どもは自分では届かず、結局親が片付けることになってしまいます。低い位置にフックを付けたり、床に近い棚を子ども専用にしたりすることで、自分でできる喜びを体験させましょう。自分で「できた!」という成功体験が、自発的な行動につながります。わが家では玄関の壁に子どもの身長に合わせて3段のフックを設置し、それぞれの子どもが自分で届く高さに上着をかけられるようにしています。
さらに、片付けを「楽しい活動」に変える工夫も効果的です。「靴を入れるとおしゃべりする箱」を作ったり、「片付けたらシールが貼れる」などのちょっとした仕掛けで、子どもは喜んで片付けに参加してくれるようになります。3人の子育てを通じて実感したのは、子どもは「強制されること」には抵抗しますが、「楽しいこと」には進んで取り組むということ。片付けも「楽しい遊び」の延長として捉えられるような雰囲気作りを心がけています。うちでは「片付けマスター認定証」を作って、一週間きちんと片付けができた子にはご褒美のシールを貼っています。子どもたちの励みになっていますよ。
狭い玄関でもあきらめない!一歩ずつ理想の空間へ
狭い玄関の収納は、一気に完璧にするものではなく、少しずつ改善していくプロセスなんです。
この記事でご紹介した「仕分ける」「垂直方向を活用する」「100均アイテムで仕組みを作る」という3つのステップは、どんなに狭い玄関でも、どんな賃貸住宅でも実践できるものばかりです。全てを一度に取り入れる必要はありません。今日からできそうな小さなことから始めて、少しずつ理想の玄関に近づけていきましょう。わたしも3人目の子どもが生まれてから玄関が物であふれかえったとき、「もう無理かも…」と思いましたが、少しずつ工夫を重ねることで乗り越えられました。
そして一番大切なのは「家族みんなが使いやすい」と感じる収納であること。インスタグラムやインテリア雑誌のような完璧な収納を目指すのではなく、あなたの家族が「これなら続けられる」と思える方法を選ぶことが長続きの秘訣です。3人の子どもを育てながら試行錯誤してきた私の経験から言えるのは、「完璧な収納」より「続けられる収納」の方がずっと価値があるということ。多少のごちゃごちゃは、賑やかな家庭の証と思えば気になりませんよ。
最後に、玄関収納の改善は「家族の心地よい暮らし」のためのものだということを忘れないでください。散らかりがちだった玄関がすっきりすると、毎日の出勤や登校がスムーズになり、帰宅時の「ただいま」の気持ちも明るくなります。そんな小さな幸せの積み重ねこそが、心地よい暮らしにつながるのだと思います。今日から少しずつ、あなたの家族にぴったりの玄関づくりを始めてみませんか?きっと素敵な毎日が待っていますよ。